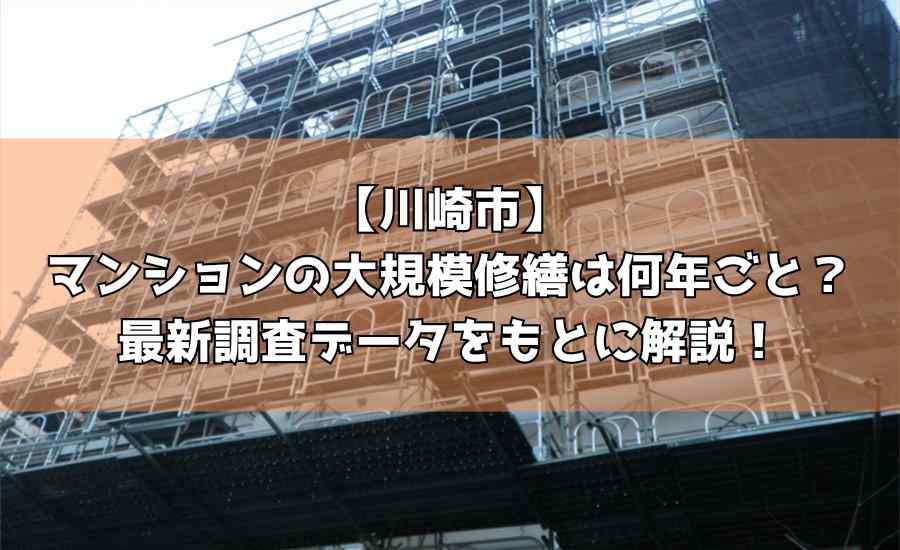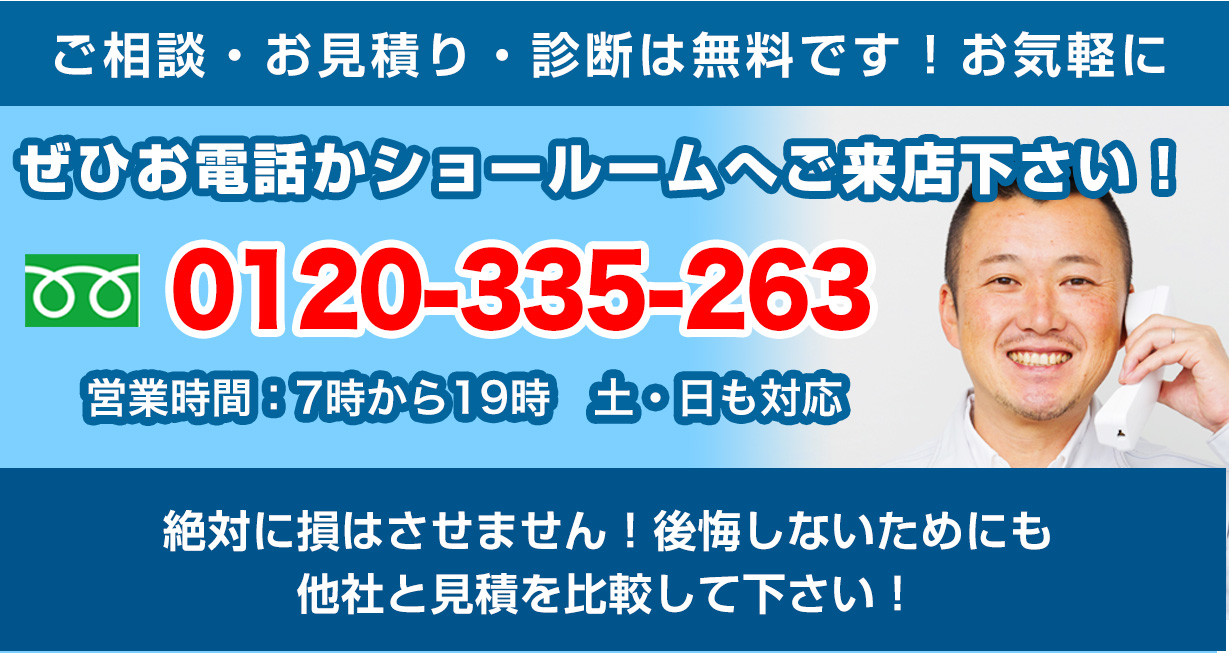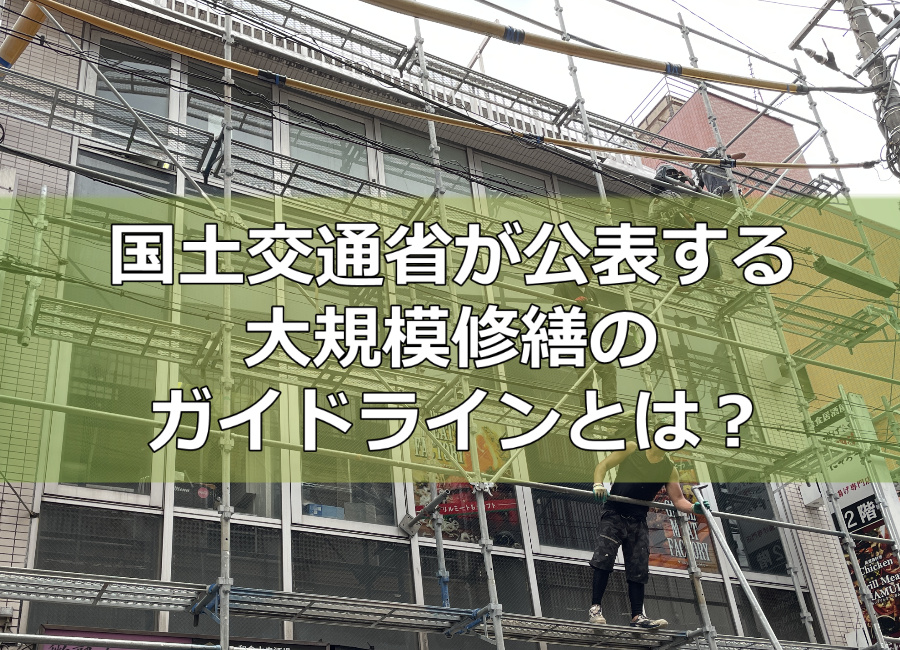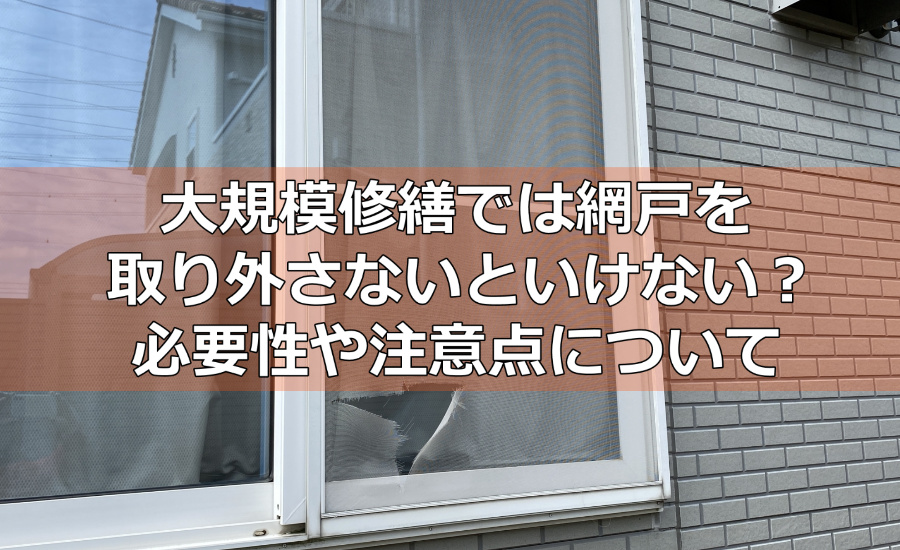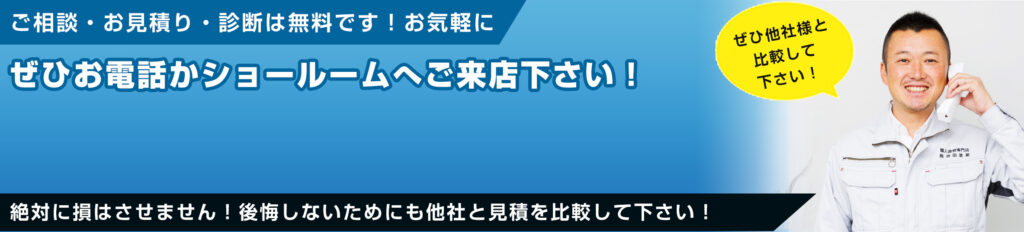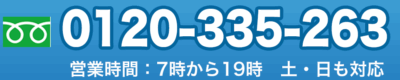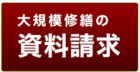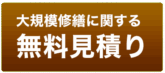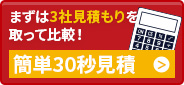マンションの大規模修繕は何年ごとに行うべきか、管理組合の方やオーナーの方にとって悩みの種ではないでしょうか?「12年ごと」「15年ごと」など、さまざまな情報がありますが、実際の修繕周期はどうなっているのでしょうか。
国土交通省の『長期修繕計画作成ガイドライン』(令和6年改定)では、大規模修繕の目安の周期が例示されています。また、『マンション大規模修繕工事に関する実態調査』(令和3年)では、1回目から3回目、4回目以降の修繕時期の平均値が示されています。
マンションの修繕周期に決まりはないのでしょうか?
本記事では、最新の調査データをもとに、最適な修繕周期の決め方、修繕積立金の考え方、修繕費用を抑えるコツについて詳しく解説します。
参考:国土交通省『令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査』『長期修繕計画作成ガイドラインマンションの修繕積立金に関するガイドライン令和6年改定内容について』
マンションの大規模修繕は何年ごと?調査データから見る実態

マンションの大規模修繕は、建物の老朽化を防ぎ、快適な居住環境を維持するために欠かせないものです。しかし、「次の修繕はいつ行うべきか?」という疑問を抱える管理組合やオーナーの方は少なくありません。
一般的には「12年ごと」「15年ごと」という目安が語られることが多いですが、実際の修繕周期はマンションによって異なります。修繕の間隔が短すぎると資金不足のリスクがあり、逆に遅すぎると建物の劣化が進み、修繕費用が増大してしまうため、適切なタイミングを見極めることが重要です。
ここからは、修繕周期の一般的な目安や、修繕時期を判断するためのポイントを詳しく解説していきます。
一般的な修繕周期の目安とは?
マンションの大規模修繕は、建物の寿命を延ばし、安全性や快適性を維持するために重要なメンテナンスですが、その周期には一定の目安があります。
国土交通省の『長期修繕計画作成ガイドラインマンションの修繕積立金に関するガイドライン令和6年改定内容について』では、大規模修繕の周期として12〜15年が例示されています。これは、建物の劣化スピードや資金計画を考慮した標準的なサイクルとして設定されていますが、すべてのマンションに当てはまるわけではありません。
実際の調査データ(令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査)を見ると、修繕周期の平均は以下のようになっています。
- 1回目の修繕:15.6年
- 2回目の修繕:14.0年
- 3回目の修繕:12.9年
- 4回目以降の修繕:13.1年
このデータからわかるように、1回目の大規模修繕は15年程度が一般的ですが、2回目以降は修繕周期が徐々に短くなる傾向があります。これは、建物が古くなるにつれて劣化の進行が早まり、より短い間隔でのメンテナンスが必要になるためです。
また、修繕周期は以下の要因によって変動します。
- 建物の構造・立地(鉄筋コンクリートの耐久性や、海沿い・高温多湿地域などの環境要因)
- 修繕積立金の状況(資金が不足すると計画どおりに修繕できない)
管理体制の違い(計画的なメンテナンスを行っているかどうか)
これらの要素を踏まえながら、自分のマンションにとって最適な修繕周期を見極めることが大切です。
令和3年度の調査データから見る最新の修繕傾向
マンションの大規模修繕は、建物の維持管理において欠かせないものですが、実際にどのようなタイミングで行われ、どの程度の費用がかかっているのかを把握しておくことが重要です。国土交通省の『令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査』では、全国のマンションを対象に修繕の実態が調査されました。
①修繕計画と実態のギャップ
多くのマンションでは、修繕計画で想定していた周期よりも実際の修繕が遅れる傾向があることがわかっています。これは、以下のような要因が影響しているためです。
- 修繕積立金の不足:予定していた工事費用を確保できず、計画の延期を余儀なくされるケースが多い。
- 管理組合の意思決定の遅れ:住民の合意形成に時間がかかり、着工までに年単位の遅れが生じることもある。
- 劣化診断の結果:当初計画よりも建物の劣化が緩やかであった場合、修繕を先延ばしする判断がなされることがある。
一方で、計画よりも早く修繕を実施したマンションも存在します。これは、外壁や防水部分の劣化が想定よりも進行していたり、耐震補強の必要性が生じたりしたケースに多く見られます。
②修繕費用の上昇傾向
調査では、修繕の回数が進むごとに1戸あたりの修繕費用が増加する傾向が確認されています。これは、単なる塗装や防水工事だけでなく、給排水管の交換や耐震補強など、より大規模な工事が必要になるためです。特に、築30年以上のマンションでは、設備の老朽化が進み、修繕費用が膨らみやすくなります。
また、近年の建築資材費の高騰や人件費の上昇も影響し、過去の修繕費用のデータをもとに計画を立てていたマンションでは、予算を超えてしまうケースも出ています。そのため、長期的な資金計画の見直しがますます重要になっています。
③修繕周期を短縮できるマンションの特徴
一方で、調査結果からは、比較的長い周期で大規模修繕を実施できているマンションの特徴も見えてきます。
- 定期的な小規模メンテナンスを実施している(劣化を抑え、突発的な大規模工事を減らす)
- 修繕積立金が計画的に確保されている(資金の不足がなく、最適なタイミングで修繕が可能)
- 管理組合の意思決定がスムーズ(合意形成が早く、計画通りに工事を実施できる)
これらの要素を備えたマンションでは、急な修繕費の増加を防ぎ、適切なタイミングで修繕を進められる傾向があります。
修繕周期が早すぎるor遅すぎるとどうなる?
マンションの大規模修繕は、適切なタイミングで実施することが重要です。計画よりも早すぎる修繕、または遅すぎる修繕には、それぞれリスクがあります。ここでは、それぞれのデメリットを詳しく見ていきましょう。
①修繕周期が早すぎる場合のリスク
大規模修繕を必要以上に早く実施すると、次のような問題が発生します。
- 修繕積立金が不足する可能性が高い→計画的に積み立てた資金が十分でないうちに修繕を行うと、追加の一時金徴収や借入れが必要になる。
- まだ使える設備を交換することで無駄なコストが発生→例えば、防水工事や塗装工事は、適切なメンテナンスを行えば数年延ばせる場合もある。
住民の負担が増し、不満が出やすい→頻繁な工事は、居住者にとって騒音や生活の制限が増えるため、合意形成が難しくなることも。 - 修繕後にさらに良い技術や材料が登場する可能性がある→例えば、より耐久性の高い塗料や省エネ効果のある設備が後に登場することがあり、早すぎる修繕ではそれらを活用できない。
このように、計画よりも早い修繕は、費用や資材の無駄遣いにつながる可能性があるため慎重な判断が必要です。
②修繕周期が遅すぎる場合のリスク
一方で、必要なタイミングで修繕を実施しないと、以下のような問題が発生します。
- 建物の劣化が進み、結果的に修繕費が高くなる→例えば、外壁のひび割れを放置すると、雨水が浸入し、補修だけで済むはずが全面改修になり、高額な費用がかかることも。
- 居住者の安全性に影響を及ぼす可能性がある→バルコニーの防水層が劣化すると漏水が発生し、鉄筋が錆びて耐久性が低下するリスクがある。
- 外観の老朽化により資産価値が低下→外壁の汚れや破損が目立つと、マンションの資産価値が落ち、売却や賃貸募集の際に不利になる。
- 急な修繕が必要になり、コストがかさむ→定期的な修繕を怠ると、突発的なトラブル(漏水、設備故障など)が発生し、予定外の出費につながる。
このように、修繕を先延ばしにすると、短期的にはコスト削減になるものの、長期的には建物の劣化が進み、結果的により大きな費用負担につながる可能性が高くなります。
③適切な修繕周期を見極めるポイント
では、適切なタイミングで修繕を実施するためにはどうすればいいのでしょうか?重要なのは、以下のポイントを踏まえて周期を決定することです。
- 定期的な建物診断を実施し、劣化の進行状況を確認する
- 修繕積立金の状況を把握し、計画的に資金を確保する
- 最新の修繕技術や材料を活用し、より長持ちする工法を検討する
- 住民の合意形成をスムーズに進めるため、早めに情報共有を行う
修繕の周期は、早すぎても遅すぎても問題が生じるため、建物の状態や資金計画を見ながら適切なタイミングで実施することが大切です。
マンションの修繕計画の立て方と周期の決め方

マンションの大規模修繕は、事前の計画がしっかりしているかどうかで、スムーズに進むか、トラブルが発生するかが決まります。
修繕周期の決定には、国土交通省のガイドラインや過去の実績データが参考になりますが、それだけでなく、マンションごとの資金状況や建物の劣化状況、住民の合意形成の進め方なども考慮する必要があります。
また、修繕計画を適切に立てることで、不要な修繕を防ぎ、必要なタイミングで適正な工事を実施できるようになるため、長期的なコスト削減にもつながります。
では、具体的にどのようにして修繕計画を立て、最適な周期を決めていけばよいのでしょうか?
ここからは、修繕周期の決め方、修繕積立金の考え方、そして修繕周期を延ばす方法について詳しく解説していきます。
修繕周期の決め方はどうすればいい?
マンションの大規模修繕は、一律に「〇年ごとに実施すべき」と決まっているわけではありません。国土交通省のガイドラインでは12〜15年周期が例示されていますが、実際の修繕周期は建物の状況や管理方針によって異なります。
では、どのような要素を考慮して、最適な修繕周期を決めればよいのでしょうか?
以下のポイントを基準にすると、より合理的な周期の設定が可能になります。
①建物の劣化状況を定期的にチェックする
修繕周期の決定には、マンションの劣化状況を正確に把握することが最も重要です。
特に以下の点を重点的に点検しましょう。
- 外壁や防水の劣化具合(ひび割れ、剥離、雨漏りの有無)
- 鉄部や給排水設備の状態(サビや配管の腐食)
- バルコニーや共用部分の傷み(床材の破損、排水不良)
定期的な建物診断を行い、修繕が必要なタイミングを見極めることが大切です。
②過去の修繕履歴を確認する
過去にどのような修繕を行ったかを整理し、前回の修繕からどれくらいの期間が経過しているかを把握することも重要です。
例えば、前回の修繕で高耐久の塗料を使用した場合は、次回の塗装工事を数年延ばせる可能性があります。逆に、前回の修繕で簡易的な補修しか行っていなければ、次の修繕を早めるべき場合もあります。
③修繕積立金の状況を考慮する
修繕積立金の蓄えが不十分な場合、計画通りに修繕を実施できないリスクがあります。
そのため、以下の点を確認しながら、現実的な修繕周期を設定することが重要です。
- 現在の修繕積立金の残高は十分か?
- 今後の積立計画で必要な費用を確保できるか?
- 積立金が不足する場合、一時金徴収や借入れの計画はあるか?
修繕積立金の不足が原因で修繕を先延ばしにすると、劣化が進み、結果的に修繕費用が高くなることもあるため注意が必要です。
④管理組合の合意形成をスムーズに進める
修繕のタイミングを決める際には、管理組合の理事会や総会での合意形成も不可欠です。
- 早めに修繕計画を住民に周知し、意見を集める
- 資金計画を明確に示し、住民の理解を得る
- 必要であれば、専門家(マンション管理士、建築士)に相談する
住民の間で意見が割れ、合意形成が難航すると、修繕の実施が遅れてしまうため、早めに議論を進めることがポイントです。
⑤最新の修繕技術を活用する
近年では、耐久性の高い塗料や防水材、省エネ型の設備など、修繕周期を延ばせる技術が増えています。例えば、以下のような選択肢があります。
- 耐久年数の長い塗料(フッ素塗料、無機塗料など)を使用→次の塗装工事を延ばせる
- 防水シートの種類を変更し、耐久性を向上→屋上防水の再施工を数年先送りできる
- LED照明や省エネ設備の導入→修繕費用を抑えつつ、ランニングコストも削減
新しい技術や材料をうまく取り入れることで、修繕周期を延ばし、長期的なコストを削減することが可能です。
修繕周期を延ばす方法はある?
大規模修繕はマンションの維持に必要不可欠ですが、頻繁に行うと費用負担が大きくなります。そのため、適切なメンテナンスを行いながら修繕周期を延ばす工夫をすることが、管理組合や住民にとって重要になります。
では、修繕周期を延ばすためにはどのような対策が有効なのでしょうか?ここでは、劣化を遅らせ、修繕コストを抑える具体的な方法について解説します。
①定期的な点検と適切なメンテナンスを実施する
小さな劣化を早めに修繕することで、大規模な改修を遅らせることが可能です。例えば、以下のようなメンテナンスが効果的です。
- 外壁のひび割れを早期補修→雨水の浸入を防ぎ、コンクリートの劣化を防ぐ
- 屋上やバルコニーの防水チェック→防水層の劣化を防ぎ、漏水を未然に防ぐ
- 給排水管の定期清掃→詰まりや腐食を防ぎ、突発的な故障を減らす
定期点検を行い、軽微な補修を早めに実施することで、大規模修繕の回数を減らし、周期を延ばすことが可能です。
②耐久性の高い資材・工法を選ぶ
修繕時に使用する資材や工法を工夫することで、次回の修繕までの期間を長くすることができます。例えば、
- フッ素塗料や無機塗料を使用する→通常の塗料よりも耐久年数が長く、塗り替え周期を延ばせる
- 防水工法を高耐久なものにする→シート防水やウレタン防水のグレードを上げ、劣化を抑える
- 耐久性の高い建材を選ぶ→外壁タイルの目地材やシール材を高品質なものに変更し、メンテナンス頻度を減らす
初期費用は高くなりますが、長期的に見ると修繕回数が減り、コスト削減につながる可能性があります。
③日常的な住民の意識を高める
住民の行動によっても、建物の劣化スピードを遅らせることができます。例えば、
- バルコニーの排水溝を定期的に掃除する→排水詰まりを防ぎ、防水層の劣化を防ぐ
- 共用部分での喫煙や火気の使用を控える→外壁の汚れや火災リスクを減らす
- エントランスや廊下の清掃を行う→汚れやカビの発生を防ぎ、美観を維持する
管理組合が定期的に住民向けの情報発信を行い、建物を大切に使う意識を高めることで、修繕の負担を軽減できるでしょう。
大規模修繕の費用を抑えるポイント

マンションの大規模修繕は、多くの費用がかかる一大プロジェクトです。国土交通省の調査によると、1回の大規模修繕にかかる費用は1戸あたり100万円以上が一般的で、築年数が経過するほどコストが増える傾向にあります。
そのため、管理組合や住民にとっては、「できるだけ費用を抑えつつ、適切な修繕を行う」ことが重要な課題となります。単純に工事費を削るのではなく、適切な計画と工夫をすることで、コストを最適化することが可能です。
ここでは、無駄な費用を削減し、効率的に修繕を行うための具体的なポイントを解説していきます。
適正な見積もりを取る方法
大規模修繕の費用を抑えるためには、適正な見積もりを取ることが不可欠です。業者によって提示金額や工事内容が異なるため、慎重に比較・検討することが重要になります。
①複数の業者から相見積もりを取る
まず、1社だけでなく、最低でも3社以上の業者から見積もりを取得することが基本です。特に、大手ゼネコン、地域の施工業者、管理会社の指定業者など、異なるタイプの業者を比較すると、相場を把握しやすくなります。同じ工事内容であっても、業者によって数十万円以上の差が出ることもあるため、慎重に選びましょう。
②見積もりの内訳を細かくチェックする
見積もり内容に「一式」と書かれている場合、どこまでの工事が含まれているのかが不明確なことがあります。そのため、資材費や人件費の内訳を細かくチェックし、不明な点は業者に質問することが重要です。「追加費用が発生する可能性はあるか?」なども事前に確認し、後から予算オーバーしないように注意しましょう。
③管理会社の見積もりを鵜呑みにしない
管理会社が指定する業者に依頼するケースもありますが、中間マージンが発生して費用が割高になることがあります。そのため、管理会社の見積もりだけでなく、独立した施工業者の見積もりも取り、適正価格かどうかを比較することが大切です。
④第三者の専門家に相談する
見積もりの適正性に不安がある場合は、マンション管理士や建築士などの専門家に相談するのも有効です。プロの視点から見積もりを精査してもらうことで、不必要な工事が含まれていないかを確認できます。特に大規模な修繕工事を予定している場合、専門家のアドバイスを受けることで、コスト削減につながる可能性が高まります。
適正な見積もりを取ることで、無駄なコストを削減し、資金を有効に活用できます。慎重な比較・検討を行い、納得のいく工事を実施しましょう。
補助金・助成金を活用する
大規模修繕工事の費用を抑えるために、国や自治体が実施している補助金・助成金制度を活用することも有効な方法の一つです。適用条件を満たせば、修繕費用の一部を補助してもらえるため、積極的に情報を収集し、活用を検討しましょう。
①補助金・助成金の種類
マンションの大規模修繕に関連する補助金・助成金には、以下のようなものがあります。
- 省エネ改修補助金:断熱性能の向上やLED照明の導入など、省エネ設備を導入する場合に支給される補助金。
- 耐震改修助成金:築年数が古いマンションの耐震補強工事を行う際に支給される助成金。
- バリアフリー改修補助金:エレベーターの設置や共用部分の段差解消など、高齢者や障がい者向けの改修を行う際に適用される制度。
- 自治体独自の補助制度:各自治体が独自に設けている修繕費用の助成制度。都市部では特に充実しているケースがある。
これらの補助金・助成金は、国の制度だけでなく、自治体ごとに異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
②補助金を活用するためのポイント
補助金・助成金をスムーズに活用するためには、いくつかの注意点があります。
まず、申請期限や要件を事前に確認することが大切です。補助金は年度ごとに募集が行われることが多く、期限を過ぎると申請できなくなるため、修繕計画の初期段階で情報収集を行いましょう。
また、申請には詳細な書類提出が求められることが多いため、業者や管理組合と連携しながら、必要な書類を準備することが重要です。特に、施工前後の写真や工事内容の詳細な報告書が必要になるケースもあるため、事前に要件を確認し、計画的に準備を進めることが成功のカギとなります。
③補助金情報の収集方法
最新の補助金・助成金情報は、以下の方法で確認できます。
- 国土交通省や各自治体の公式ホームページをチェックする
- マンション管理士や専門業者に相談する
- 管理組合向けのセミナーや説明会に参加する
補助金をうまく活用すれば、修繕費用の負担を大幅に軽減できる可能性があります。少しでもコストを抑えるために、積極的に情報を集め、利用できる制度を活用しましょう。
居住者との合意形成をスムーズに進める方法
大規模修繕工事を円滑に進めるためには、居住者の理解と協力を得ることが不可欠です。しかし、工事費用の負担や工事中の生活環境の変化などに対して、意見が分かれることも少なくありません。スムーズに合意形成を進めるためには、適切な情報提供と話し合いの場を設けることが重要です。
①早めの情報共有が合意形成のカギ
修繕計画を住民に伝えるのが遅れると、不信感や反発を招きやすくなります。理事会や総会で定期的に進捗を報告し、必要に応じて説明会を開くことで、住民の理解を深めましょう。また、修繕の必要性を明確に伝えることも大切です。例えば、建物診断の結果を示し、修繕を遅らせるとどのようなリスクがあるのかを具体的に説明することで、住民の納得感を高めることができます。
②住民の意見を反映し、納得感を高める
一方的に決められた修繕計画では、住民の反発を招きやすくなります。事前にアンケートを実施し、工事内容やスケジュールについて意見を募ることで、「自分たちの意見が反映されている」と感じてもらいやすくなります。さらに、工事中の騒音や不便さへの配慮についても説明し、住民の不安を和らげることが重要です。
③修繕後のメリットを伝える
費用負担が発生する修繕工事に対しては、「どんなメリットがあるのか?」を明確に伝えることが、合意形成をスムーズに進めるポイントになります。外観の改善による資産価値の向上、快適な住環境の維持、修繕の先延ばしによる追加コストの回避など、修繕によるプラスの効果を具体的に説明することで、前向きな合意を得やすくなります。
住民の意見を尊重しながら、透明性を持った情報共有を行うことで、修繕工事をスムーズに進めることができます。
まとめ~川崎市のマンションの大規模修繕なら
本記事では、マンションの大規模修繕の周期や、修繕計画の立て方、費用を抑えるポイントについて詳しく解説しました。
修繕周期は一律ではなく、建物の劣化状況や修繕積立金の計画によって異なります。国土交通省のガイドラインでは12〜15年周期が例示されていますが、実際の調査データでは1回目が約15. 6年、2回目以降は周期が短くなる傾向が見られます。適切なタイミングで修繕を行うためには、定期的な建物診断と資金計画の見直しが不可欠です。
また、修繕費用を抑えるためには、適正な見積もりの取得や補助金の活用、住民との合意形成を円滑に進めることが重要です。早めに情報共有を行い、住民の意見を取り入れながら修繕計画を立てることで、トラブルを防ぎつつ、スムーズに工事を進めることができます。
マンションの長期的な資産価値を維持するためにも、計画的な修繕と適切な管理を心がけましょう。
マンションの大規模修繕工事のことなら、神奈川県川崎市の地元に20年以上密着し、4,000件超の豊富な実績を持っている大規模修繕専門店『アパマン修繕プロ』にご相談ください。
まずは、『大規模修繕・マンション修繕&防水工事専門店ショールーム』にお気軽にお越しください。
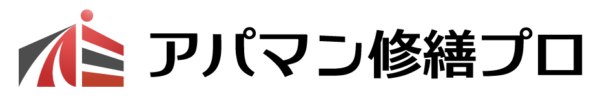

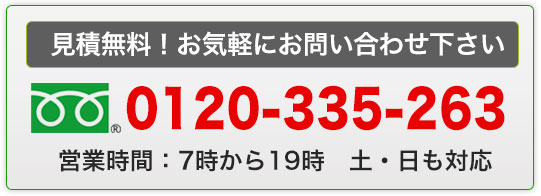
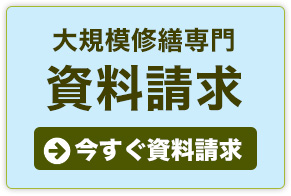

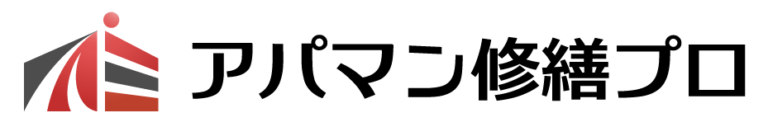

.png)