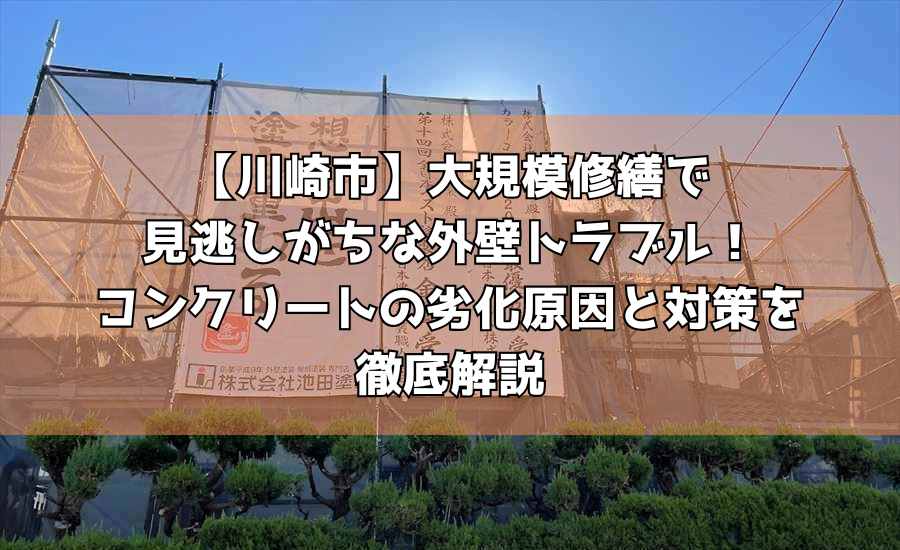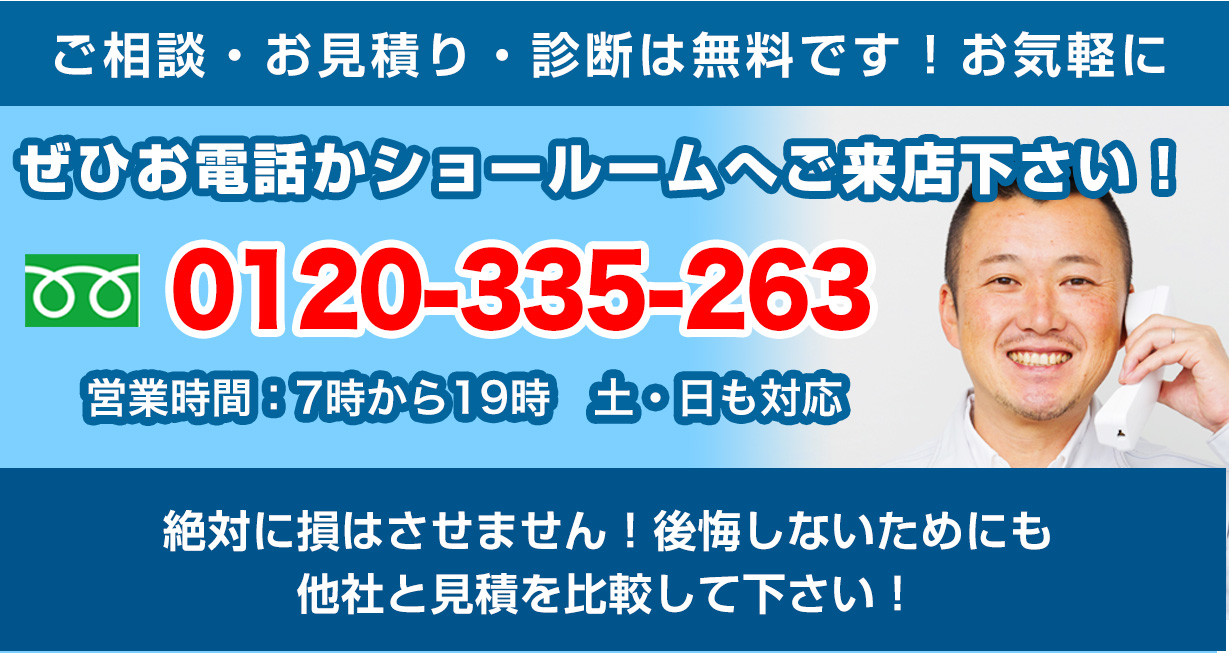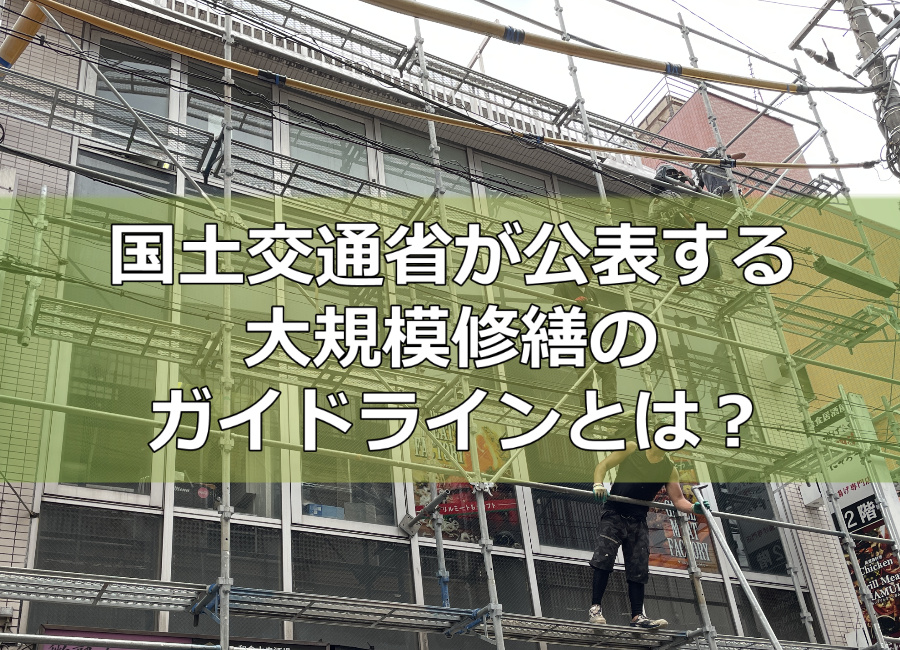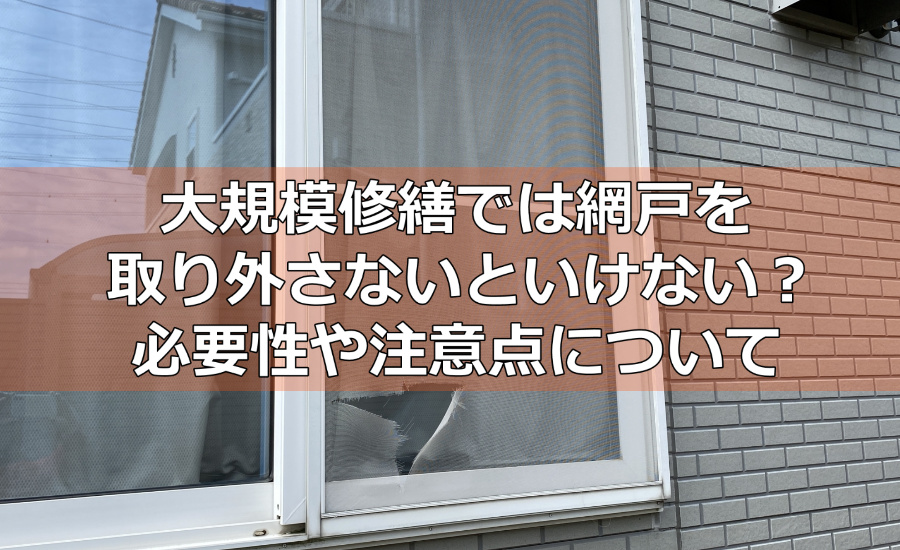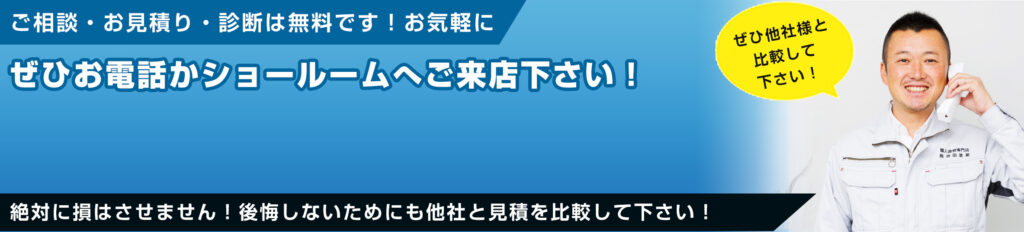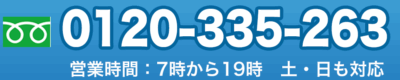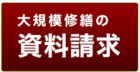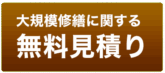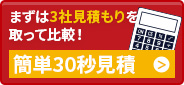「マンションの外壁にヒビが入っているけど、これって放っておいて大丈夫?」
こんな不安を抱えているマンション管理組合の方は少なくありません。特に大規模修繕のタイミングでは、外壁の見た目だけでなく“中身”の劣化も見逃せない重要なチェックポイントです。見た目はきれいでも、内部のコンクリートにはじわじわと進行する劣化が潜んでいることもあるのです。
実は、大規模修繕で“後悔”が生まれる原因のひとつに、こうした「外壁・コンクリートのトラブル見落とし」があります。クラック(ひび割れ)や浮き、剥離(はくり)などの症状は、早期に発見して対処することで費用も抑えられ、長期的に安全性を確保することができます。
この記事では、マンションの大規模修繕で見逃されがちな外壁トラブルに焦点を当て、その原因と対策方法をわかりやすく解説します。修繕の計画段階から、業者選び、実際の工事監理に役立つ具体的な情報をお届けします。
※マンションの大規模修繕で行う外壁工事の内容について、詳しく知りたい方は『【川崎市】マンションの大規模修繕で行う外壁工事とは?内容と劣化症状を徹底解説』をご覧ください。
大規模修繕で見逃されがちな外壁トラブルとは?

マンションの大規模修繕では、外壁の見た目や塗装の剥がれといった“目に見える部分”ばかりに注意が向きがちです。しかし、実際にはコンクリートの内部にひび割れや浮き、剥離といった「隠れたトラブル」が潜んでいることも少なくありません。
こうした劣化は、建物の耐久性や安全性に直接関わる重要な問題です。特に築15年以上経過したマンションでは、コンクリートの劣化が進んでいても気づかれずに放置されているケースが多く見受けられます。
ここでは、大規模修繕の現場でよく見逃されがちな外壁トラブルとその特徴について詳しく解説していきます。
クラック(ひび割れ)の種類と危険度
マンションの外壁に見られるクラック(ひび割れ)は、一見すると大きな問題には見えないかもしれません。しかし、その種類によっては建物の構造に深刻な影響を及ぼす可能性があります。クラックには大きく分けて「構造クラック」と「非構造クラック」の2種類があり、それぞれ性質と対処法が異なります。
非構造クラックとは、主に乾燥や温度変化によって表面にできる細かいひび割れのことです。幅が0.3mm未満のものが多く、すぐに建物の安全性に関わるわけではありませんが、防水性が低下するため放置は禁物です。雨水が浸入することで内部の鉄筋が錆び、劣化が進行するリスクがあります。
一方、構造クラックは、建物の荷重や地震の揺れなどにより、コンクリート内部まで亀裂が入ってしまう深刻な状態を指します。幅が0.3mmを超えるものや、斜め・縦にまっすぐ走るクラックが多く、放置すると建物の耐震性や安全性に関わる重大な問題に発展します。
修繕の際には、クラックの「幅・深さ・走行方向」を正確に調査し、必要であれば補修材やエポキシ樹脂注入などの対処を行う必要があります。専門業者による診断を受け、どのタイプのクラックなのかを見極めることが、的確な対応につながります。
爆裂・剥落(はくらく)症状とは?
外壁のコンクリートにおける「爆裂」や「剥落(はくらく)」は、放置すると非常に危険な劣化症状の一つです。とくに高層マンションでは、外壁の一部が落下することで通行人に被害を及ぼす恐れもあり、早期の発見と対応が求められます。
爆裂とは、コンクリート内部の鉄筋が錆びて膨張し、内側から圧力がかかってコンクリート表面が割れる現象です。この状態になると、外壁の表面に丸く膨れ上がったような部分が現れ、やがて一部が剥がれて落ちてしまうことがあります。雨水が侵入しやすい場所や、防水処理が不十分だった箇所に発生しやすいのが特徴です。
剥落は、爆裂の結果として起こることもありますが、施工時の不備や経年劣化が原因でコンクリートや塗膜が外壁から浮き、剥がれて落下するケースもあります。特に塗装の下地処理が不十分だった場合や、以前の修繕で応急処置だけを行っていた部分に発生しやすい傾向があります。
これらの症状は、目視での確認だけでなく、専門業者による打音検査(表面を叩いて音の変化を確認する方法)や赤外線カメラを使った浮き調査によって早期発見が可能です。剥落の危険がある箇所は迅速に補修を行い、場合によっては足場やネットを設置して安全対策を徹底することが必要です。
カビ・塗膜浮き・雨漏りの前兆
外壁にカビが発生していたり、塗装面が膨らんで浮いていたりするのを見かけたことはありませんか?これらは、建物内部にトラブルが進行しているサインであり、放置すると雨漏りや構造の劣化につながる恐れがあります。
まず、外壁に発生するカビやコケは、雨水や湿気が壁面に長くとどまっている証拠です。通常、外壁材や塗装には防水性がありますが、経年劣化によって表面の防水機能が低下すると、水分が染み込みやすくなります。その結果、外壁の内側に湿気がこもり、カビが繁殖しやすい環境が生まれるのです。
また、塗膜の浮きや膨らみは、塗装の下地であるモルタルやコンクリートとの密着が弱まっている状態です。これは、塗装の施工不良や、コンクリート内部に浸入した水分が蒸発し、圧力で表面を押し上げてしまうことが原因とされます。これが進行すると、表面の塗膜が剥がれ落ちるだけでなく、内部の躯体にも影響を及ぼす可能性があります。
こうした症状を見逃すと、建物内部への水の浸入が進み、最終的には雨漏りという形で現れてしまいます。特に目に見えるカビや塗膜の異常は、「まだ大丈夫」と思わずに、早めに専門業者に調査を依頼することが重要です。
劣化の原因別のメカニズムと対策

外壁トラブルの発生には、必ず何らかの原因があります。ただ単に経年劣化と片付けてしまうのではなく、原因を正確に理解することで、的確な対策を講じることができます。とくにコンクリート構造の場合、見た目では分かりづらい内部の変化が進行していることも少なくありません。
本章では、外的な環境要因から内部の化学的変化、さらには施工不良まで、コンクリート外壁の劣化を引き起こす代表的な原因を取り上げ、それぞれに適した修繕・予防方法について詳しく解説していきます。原因に応じた対策を知っておけば、修繕工事の精度も大きく向上し、長期的な建物の維持管理に大きく役立ちます。
外的要因:凍結・融解による膨張と収縮
日本の中でも特に寒冷地に建つマンションでは、冬季における「凍結と融解」の繰り返しが、外壁コンクリートの劣化を早める大きな要因となります。この現象は「凍害(とうがい)」とも呼ばれ、外壁に含まれた水分が凍ることで体積が膨張し、融解時に収縮することで、コンクリート内部に微細なクラックが生じるというものです。
この膨張と収縮の繰り返しが積み重なると、やがて目に見えるひび割れや表面の剥離へと発展していきます。特に日当たりの悪い北側の壁面や、雨水がたまりやすい窪みのある部分では、この現象が起きやすいとされています。
凍害への対策としては、まず外壁表面の防水性を高めることが第一です。具体的には、防水塗装や撥水材の塗布によって水分の浸入を防ぐ施工を行うこと。また、下地に空気を含みやすい軽量モルタルを使用している場合は、事前に浮きやひび割れのチェックを入念に行う必要があります。
さらに、凍結深度(地面が凍る深さ)を考慮した設計がなされていない建物では、外構部分の排水性も見直しが必要です。劣化が進行する前に早めに対策を講じることで、修繕費用を大幅に抑えることができるでしょう。
中性化による内部鉄筋の錆
コンクリート建造物における代表的な劣化原因の一つに、「中性化」があります。これは、大気中の二酸化炭素がコンクリートに浸透し、内部のアルカリ性が低下していく現象です。本来、コンクリートは強いアルカリ性(pH12〜13)であることで内部の鉄筋を錆から守っています。しかし、このアルカリ性がpH9以下に下がると、鉄筋は酸化しやすくなり、錆が発生してしまいます。
鉄筋が錆びると、その体積は約2〜3倍に膨張します。この膨張が周囲のコンクリートに圧力をかけ、ひび割れや爆裂といった劣化を引き起こすのです。特に中性化は、外見からでは進行の程度を把握しづらいため、見逃されやすいのが厄介な点です。
中性化の進行を調査するには、専用の試薬を用いた「中性化深さの測定」が有効です。コンクリートの一部をコア抜きし、フェノールフタレイン試薬をかけることで、アルカリ性が保たれているかどうかを色の変化で判断できます。
対策としては、外壁の表面に浸透性防水材や表面被覆材を塗布することで、二酸化炭素の浸入を防ぐ方法が一般的です。また、中性化が進行してしまった場合には、鉄筋の錆を除去した上で断面修復材を用いた補修を行う必要があります。適切なタイミングでの調査と処置が、建物の長寿命化に大きく貢献します。
施工不良・下地処理不足による剥離
外壁工事において、仕上がりがきれいでも「下地処理」が不十分だと、数年後に塗膜やモルタルの剥離が起こる可能性があります。こうした劣化は、施工当初の不備が原因であるケースが多く、長期的には深刻なトラブルへとつながります。
下地処理とは、塗装や補修の前に外壁表面を清掃・整備し、塗料や補修材がしっかりと密着する状態に整える作業です。たとえば、旧塗膜の除去、高圧洗浄、クラック補修、鉄筋の防錆処理などが該当します。これを省略したり、簡略化したりすると、後から塗った塗料が浮いたり、モルタルが剥がれたりしてしまうのです。
とくに問題となるのは、見た目では「仕上がっている」ように見えるため、施主や管理組合側が気づきにくい点です。完成後1〜3年以内に塗膜の浮きやひび割れが現れる場合、それは下地処理の不備を疑うべきサインといえるでしょう。
このようなトラブルを防ぐには、施工前にしっかりと工程表を確認し、下地処理にどれだけの時間と人手がかかるのかを把握することが重要です。また、施工中も適切な写真記録や報告が行われているかをチェックし、不安があれば途中で第三者機関に診断を依頼するのも一つの手段です。
適切な下地処理を行うことは、外壁の耐久性と美観を長く保つうえで不可欠です。施工品質に対する意識を高めることが、トラブルを未然に防ぐ第一歩となります。
見逃さないためのチェック方法と検査ポイント

大規模修繕における失敗の多くは、「劣化の見落とし」から始まります。見た目に異常がなくても、内部ではじわじわと劣化が進行しているケースも少なくありません。だからこそ、修繕を成功させるためには、工事の前段階である「調査・診断」が極めて重要です。
とくに外壁のコンクリート部分は、劣化の初期症状を早期に発見できるかどうかで、補修の範囲や費用、さらには建物の寿命そのものに大きく影響します。ここでは、管理組合の担当者でも確認できるチェックポイントから、専門業者による検査方法まで、見逃しを防ぐための具体的な方法を詳しくご紹介します。
目視&赤外線カメラによる事前調査
外壁の劣化を確認するための最も基本的な方法は「目視調査」です。建物の外側をじっくり観察することで、クラック(ひび割れ)、塗膜の剥がれ、カビや汚れの付着など、さまざまな異常を発見できます。特に目立つのは、外壁に直線的に走る亀裂や、モルタルの膨れ、塗装の変色などです。
ただし、目視だけでは限界があります。外壁の“内部”にある浮きや剥離は、表面からは見えないことも多く、こうした隠れたトラブルを把握するには「赤外線カメラ調査」が有効です。これは、壁面の温度差を可視化することで、内部に空洞がある箇所や、密着性が失われた部分を発見する技術です。
赤外線カメラを使うことで、肉眼では見えない浮きや劣化部位を正確に捉えることができます。特に太陽が当たった後の夕方など、温度差が出やすい時間帯に行うと、より精度の高い診断が可能です。
また、これらの調査は、修繕の範囲や見積もりに大きく影響するため、工事前には必ず実施しておきたい工程です。管理組合としては、業者から提出された調査報告書の内容を確認し、不明点があれば説明を求める姿勢が大切です。
打音検査(ハンマーテスト)のやり方
外壁の内部にある「浮き」や「剥離」の状態を確認するために、非常に効果的なのが「打音検査(ハンマーテスト)」です。これは、鉄製やゴム製のハンマーで外壁を叩き、その音の違いによってコンクリートの密着状況を判断する方法です。
密着している部分を叩くと「カンカン」と高い音がする一方で、内部が浮いている箇所では「ボコボコ」「鈍い音」など、音がこもったように聞こえます。経験を積んだ診断員であれば、この音の違いを敏感に聞き分け、どこに問題があるのかを即座に把握できます。
特に、クラックの周辺や、以前補修された箇所は再劣化しやすいため、重点的に打音検査を行うのが効果的です。また、打音検査は比較的簡易に行えるため、足場を組んだタイミングでの定期的な実施が推奨されます。
ただし、打音検査には専門性が求められます。誤って浮いていない部分を削ってしまったり、補修が不要な箇所まで工事を広げてしまうリスクもあるため、必ず実績のある業者に依頼することが重要です。報告書では、どの範囲に浮きがあるのか、図面付きで明示されることが望ましく、診断精度の高さが施工品質にも直結します。
サンプリング&コア抜き検査の必要性
コンクリートの内部状態を正確に把握するためには、目視や打音検査だけでは不十分な場合があります。そうした時に必要となるのが、「コア抜き検査」と呼ばれる物理的な調査方法です。
コア抜きとは、コンクリートに専用のドリルを使って円筒形の試料(コア)を取り出し、その内部構造や強度、中性化の進行具合などを確認する調査です。この検査により、見た目では判断できない鉄筋の錆び具合や、コンクリート自体の劣化度が明確になります。
たとえば、フェノールフタレインという試薬を使うと、中性化の深さを視覚的に確認することができます。アルカリ性が保たれている部分は赤く染まり、中性化が進んでいる箇所は無色になるため、劣化の進行具合を一目で判断できます。
この検査は外壁の一部を破壊する必要があるため、全体ではなく代表的な数カ所を選んで行うのが一般的です。調査後は穴を適切に補修し、見た目や防水性に問題が出ないように施工する必要があります。
コア抜き検査の実施には費用と時間がかかりますが、正確な診断結果が得られるため、修繕計画の精度を大きく高める効果があります。とくに築年数が長く、目に見える劣化が多いマンションでは、積極的な実施を検討すべき重要な調査です。
まとめ~川崎市のマンションの大規模修繕なら
本記事では、マンションの大規模修繕において見逃されがちな外壁トラブル、特にコンクリートの劣化症状とその原因、対策方法について詳しくお伝えしました。
外壁のクラックや爆裂、塗膜の浮きといった初期症状を早期に発見し、適切に対処することが建物の長寿命化には欠かせません。また、調査段階での検査精度や、業者選びの見極め、工事中の報告体制といった一連の流れを丁寧に管理することで、無駄なコストや施工ミスを防ぐことができます。
マンションの維持管理を任される管理組合の皆さまにとって、今回の内容が「何を見て、どう判断すべきか」の参考になれば幸いです。まずは現在の外壁の状態をチェックし、必要に応じて専門業者に調査を依頼してみるところから始めてみてはいかがでしょうか。
マンションの大規模修繕工事のことなら、神奈川県川崎市の地元に20年以上密着し、4,000件超の豊富な実績を持っている大規模修繕専門店『アパマン修繕プロ』にご相談ください。
まずは、『大規模修繕・マンション修繕&防水工事専門店ショールーム』にお気軽にお越しください。
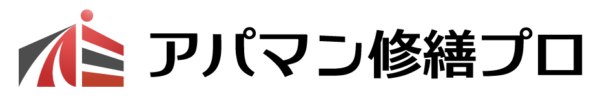

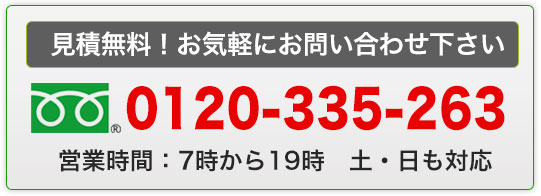
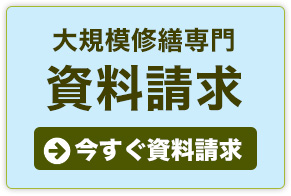

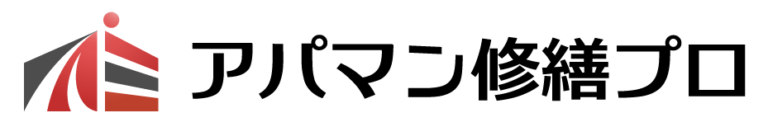

.png)